今回は医師国家試験対策(国試対策)として造血幹細胞移植についての知識を整理していきたいと思います。造血幹細胞移植は、正解選択肢としての出題はほとんどありませんが、誤答選択肢としてはしばしば出題されており、知識があやふやだと自信を持って選択肢を選ぶことができません。今回の記事で国試問題を解くために最低限必要な知識やイメージをまとめましたので、確認問題を解きながら知識を定着していただけましたら幸いです。それでは、はじめていきましょう。
造血幹細胞とは
まず初めに、造血幹細胞の特徴について復習しましょう。造血幹細胞とは、骨髄とよばれる血球の製造工場に存在して、赤血球・白血球・血小板にそれぞれ分化したり(多分化能)、造血幹細胞自身の数を増やしたり(自己複製能)、私たちの正常造血に不可欠な存在となっております。国家試験では、造血幹細胞が多分化能と自己複製能を持つことは複数回出題されていますが、その他にも中胚葉由来であること、表面抗原(細胞膜に発現しているタンパク質)としてCD34が陽性であること、末梢血中にも僅かに存在すること、好中球を増やすために使用されるG-CSF(顆粒球コロニー形成刺激因子)製剤の投与により末梢血中に増加すること(後述の末梢血移植における幹細胞採取時に行われる処置)、などが出題されていますので覚えておきましょう。

確認問題①

答 (95A-35) a (108B-7) c
造血幹細胞は中胚葉由来でした。詳しくは発生学の内容ですので割愛しますが、心臓・血管・リンパ管などの循環系は中胚葉由来であり、血液も同じく中胚葉由来です。
私たちのような成人の造血の場は骨髄でしたが、胎児は違います。胎児では、卵黄嚢→肝臓→骨髄のように主要な造血の場が推移していくのでした。胎児では、妊娠7-8ヶ月(妊娠後期)で骨髄が主要な造血の場になります。
造血幹細胞移植について
次に造血幹細胞移植についてまとめていきます。私自身の話ですが、造血幹細胞移植については教科書や参考書に書いてあるものの、初めて造血幹細胞移植の現場に立ち会わせていただけるまで、ぼんやりとしたイメージしかもてなかったです。皆様はどうでしょうか。学習を進める上で”いつ”、”何の目的に”、”どんな種類を”、”どんな疾患に”などをイメージしておくと理解が深まりますので、ぜひ意識してみてください。
造血器腫瘍の治療の流れ
造血幹細胞移植は造血器腫瘍を中心に造血器疾患の治療中に行います。以下に示しましたように、造血器腫瘍の一般的な治療は、化学療法を中心にして寛解導入療法→地固め療法→維持療法の流れで行います。寛解導入療法では、腫瘍細胞数を可能な限り減少させ、無症状で臨床的に腫瘍細胞の検出ができなくなる状態、いわゆる完全寛解(CR)を目指します。CRに達した後は、地固め療法や維持療法を駆使して、可能な限りCRの状態を維持していくのですが、ここで注意しなくてはならないことは、CR = 根治 ではないということです。CRの状態となっても、血液中には検出されないほどの僅かな腫瘍細胞が存在しており、この残存した腫瘍細胞はいずれの造血器腫瘍の再発・再燃へとつながってしまいます。CRとは治療が不必要になった完治を意味するものではなく、病気の勢いを抑え込めている状態と理解するとイメージがしやすいでしょう。

ここで治療の選択肢として存在するのが造血幹細胞移植です。造血幹細胞移植では、初回治療後の腫瘍細胞がある程度減少した時期に、前処置とよばれる強力化学療法と全身放射線照射を組み合わせた処置を行い、正常な造血能もろとも腫瘍細胞を壊滅させます。腫瘍細胞はなくなりましたが、好中球も0となるように正常造血能もありませんから、そのままでは生きていけません。そのため、ドナーから造血幹細胞をもらい、ドナーの造血幹細胞を利用して正常造血能を回復させていきます(生着)。移植を用いない化学療法のみの治療では、正常造血能を考慮しなくはならないため、造血幹細胞移植を用いた治療ほど、腫瘍細胞を壊滅させることができません。そのため、造血幹細胞移植は、造血器腫瘍に対する普及した治療法の中で、長期的なCR状態の維持を期待できる唯一の治療法となっています。

実際の現場のイメージとしましては、無菌室にいらっしゃる患者様に造血幹細胞の入ったパックを経静脈的に点滴していきます。見た目だけでは輸血と変わりませんが、移植に伴う管理が多くありますので、血液内科医はいつでも駆けつけることができる状態になっております。初めて造血幹細胞移植の現場に立ち合わせていただけた際、ドナーの方の思いを引き継いで、今まさに患者様の未来が開けて行こうとする瞬間に胸が熱くなったことを鮮明に覚えています。
造血幹細胞移植の種類
造血器疾患における造血幹細胞移植は、以下に示しましたように主に4種類の方法が実施されています。誰から造血幹細胞をもらうのかの観点で、自家移植(自分から)と同種移植(家族や他人から)に大別されます。さらに、どのような方法で造血幹細胞を採取するのかによって、末梢血移植、骨髄移植、臍帯血移植に分類されます。それぞれの分類や組み合わせで、同じ造血幹細胞移植であっても特徴が異なりますが、国家試験では出題されないでしょうから割愛して別の機会に記事にさせていただきます。

造血幹細胞移植の適応
長期的なCR状態を期待できる造血幹細胞移植ですが、全ての患者に適応となるとは限りません。前処置による感染症や移植後のGVHDなどを代表に様々な原因で治療関連死となるリスクが非常に高いです。そのため、移植実施の前には、患者の年齢や全身状態(身体機能、合併症)、患者の希望、実施施設状況などを参考に、移植可能か否かを総合的に判断しています。
移植方法のなかでも同種移植は、自家移植にはないドナーの免疫細胞による移植片対白血病効果(GVL効果)が期待されるため、高い抗腫瘍効果が見込めます。一方で、移植後の拒絶やGVHDによる治療関連死のリスクも高く、ハイリスクハイリターンの治療法といえるでしょう。
また、同種移植の際には、ドナーとなる適切な人物がいるかが問題になってきます。この際に、体内のほぼ全ての細胞表面に発現しているタンパクであるHLA(ヒト白血球抗原)が患者とドナー間でどの程度一致しているかが重要となります。HLAが適合していない場合、移植したとしても拒絶や重症GVHDとなるリスクが上昇してしまいます。

以下には、造血器腫瘍診療ガイドラインを参考に移植実施の目安をまとめました。どの疾患においても、寛解導入療法後や再発・難治例で実施されるようなアルゴリズムになっております。また、国家試験では、推奨されている年齢を守ってきますので、年齢が外れている瞬間に造血幹細胞移植の選択肢は除外することができます。

確認問題②

答 (91A-76) a,e (101B-106) e
骨髄提供者、いわゆるドナーに関して、ます重要となるのはHLA(ヒト白血球抗原)の適合度でした。補足ですが、日本では2000年以降、移植前後に特別な処置を加えることでHLAが合致していなくても同種移植が可能となった、いわゆるハプロ移植(HLA半合致移植)が実施数を伸ばしています。また、造血幹細胞移植に限ったことではないですが、ドナーの方にも幹細胞採取によるリスクが伴いますので、年齢が低すぎたり高すぎたりすることは好ましくありません。
成人で同種造血幹細胞移植を実施する疾患は、急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病の2トップであることを覚えておきましょう。この問題では、丁寧に急性リンパ性白血病の第一寛解期と明記してあります。一方で、慢性リンパ性白血病は、無治療や通常の化学療法で長期生存が期待できる疾患であり、同種造血幹細胞移植は一般的には行われません。しかし、若年者で治療抵抗性の慢性リンパ性白血病では、根治目的に実施せれることがあるそうです。ちなみに、不応性貧血は骨髄異形成症候群の亜型であり、中等症の再生不良性貧血とともに移植適応は一般的にはありません。多発性骨髄腫は自家移植の適応となります。
確認問題③

答 a,e
慢性骨髄性白血病の治療の基本はチロシンキナーゼ阻害薬(TKI)ですが、若年例で急性転化時には積極的に同種造血幹細胞移植を検討するそうです。ただし、慢性骨髄性白血病の急性転化例は移植をしたとしても予後が非常に悪いということも覚えておきましょう。本問題は、正解選択肢として造血幹細胞移植が選ばれた非常に稀な問題でした。造血幹細胞移植が正解選択肢となる問題はあまり出題されないため、他の選択肢を全て消去してから選択する方が無難だと思います。
移植前後に必要な管理
国家試験の出題を踏まえて、その他に整理した方が望ましいこととして、移植前後に必要な管理が挙げられます。先にも簡単に述べましたが、造血幹細胞移植には、前処置による骨髄抑制(血球減少)やそれに伴う感染症、ウイルスの再活性化、拒絶やGVHD、肝中心静脈閉塞症/肝類洞閉塞症(VOD/SOS)など様々な治療関連死に結びつく合併症が存在します。国家試験にこれまで出題されたものでは、感染症とGVHDに関する問題がありましたので紹介していきます。
確認問題④

答 e
深在性真菌感染症とは、皮膚の表面のような部位ではなく鼻、副鼻腔、肺、脳などにおける真菌感染症のことです。免疫不全者に特に起こりやすいことで知られています。どの選択肢も抗がん剤による骨髄抑制(血球減少)が起こり、感染症のリスクが高まりますが、同種造血幹細胞移植が最も感染症のリスクが高いです。前処置の副作用で口腔粘膜障害が生じやすいこと、好中球減少の期間が長いこと、GVHD予防に免疫抑制剤を使用することなどが原因に挙げれれます。そのため、同種造血幹細胞移植の実施時には抗菌薬(キノロン系)、抗真菌薬(フルコナゾールなど)、抗ウイルス薬(アシクロビルなど)を予防投与、移植実施後はST合剤投与やサイトメガロウイルス抗原検査などを適宜行います。
確認問題⑤

答 (95D-7) a (101A-18) a,c
GVHD(移植片対宿主反応)とは、ドナー由来のT細胞が患者の全身臓器を攻撃してしまう造血幹細胞移植の代表的な合併症です。その発症時期でおよそ100日以内なら急性GVHD、およそ100日以降なら慢性GVHDとよばれます。障害が起きる部位も、急性GVHDは皮膚・肝臓・消化管に起こりやすく、慢性GVHDは皮膚・肝臓・消化管に加えて、肺や分泌腺などの全身臓器にわたります。シクロスポリンやタクロリムス、メトトレキサートなどの免疫抑制剤を使用することで発症を予防できると報告されていますが、移植後にはGVHDが生じていないかを確認するために長期的なフォローが必要なことを覚えておきましょう。
GVHDの皮膚症状の問題ですが、移植後3週間とありますので急性GVHDと分かります。急性の皮膚症状なので赤く腫れる(むくむ)ことをイメージすることができれば回答できるのですが、学生で急性GVHDの皮膚症状について精通している方は滅多にいないと思います。私の尊敬する偉い先生はこのようにおっしゃていました。
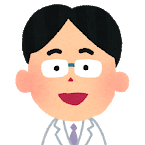
僕らは経験するからすぐ分かるんだけどね〜
まさに一見は百聞に如かずですね。
まとめ
以上、国家試験に出題される造血幹細胞移植関連の問題を効率良く解くための知識をまとめていきました。今回の記事を参考に、少しでも造血幹細胞移植についての苦手意識をなくしていただけましたら幸いです。最後までお読みになっていただき、ありがとうございました。

(参考)
・神田善伸. 血液病レジデントマニュアル第3版. 医学書院.
・一般社団法人 日本造血細胞移植データセンター 2019年度 日本における造血幹細胞移植の実績




コメント